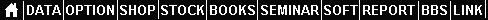
|
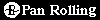
|
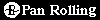 |
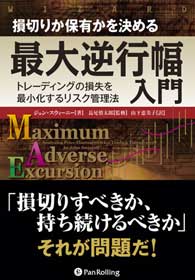 『損切りか保有かを決める最大逆行幅入門
『損切りか保有かを決める最大逆行幅入門
2012年10月発売/A5判 206頁
ISBN 978-4-7759-7166-6 C2033
定価 本体7,800円+税
著 者 ジョン・スウィーニー
監修者 長尾慎太郎
訳 者 山下恵美子
●MAE(最大逆行幅)、MinFE(最小順行幅)、MaxFE(最大順行幅)の定義と算出法
●MAEのグラフ化――データの収集、度数図、損切りサイズ
●必要資金額の決定――資産の保全とドローダウン
●損切り水準別利益――利益のトレードオフ、利益曲線
●ボラティリティの変化による影響――微調整、レンジやボラティリティの変化に伴う損切り水準の変更
●トレード管理――ポートフォリオ化の影響、日々の管理
本書は計算例や実例が豊富で、独自のチャート作りに役立つエクセルコードも充実しており、MAEを効果的に使って利益を出すための方法を指南する決定的ガイドになっている。
「本書はこれまで見過ごされてきたテーマ――どうすれば損失を最小化できるか――に焦点を当てたものだ。ジョン・スウィーニーのアドバイスに従い、損失を最小化する方法を自分のものにすれば、人より一歩も二歩も先を行くことができる」
――マーティン・J・プリング(国際経済研究所所長)
「ジョン・スウィーニーはまたしてもやってくれた。『キャンペーン・トレーディング』に引き続き、彼は本書でも複雑なアイデアを簡単で理解しやすく、トレーダーたちが情報に基づくトレーディングの意思決定を行える形で説明してくれている」
――――クリフォード・シェリー博士(『マセマティクス・オブ・テクニカル・アナリシス』の著者)
 原書『Maximum Adverse Excursion』
原書『Maximum Adverse Excursion』
|
監修者まえがき The Trader's Advantageシリーズより本書出版に寄せて はじめに
第1章 アイデア経験ルール データ
第2章 MAEとは逆行と順行MaxFEとMinFE 損切りの微調整 計算例
第3章 MAEのグラフ化データの収集度数図 損切りとドテン ビンの大きさはどれくらいが適切か 売りと買い
第4章 ビンごとの利益の算出トレードオフ問題利益曲線 グラフの解釈
第5章 ボラティリティの変化による影響微調整損切りの位置を変更させるものは値幅か、それともボラティリティか 値幅とボラティリティ 値幅の20日移動平均との比較 仕掛け日における値幅の20日移動平均との比較 MAEと仕掛け日の値幅 問題はまったくないのか まとめ |
第6章 連続逆行が及ぼす影響資産の保全特定のトレーディング戦術に対する影響 連敗の頻度 計算方法 もっと保守的な基準 トレードを始めてすぐに大きなドローダウンが発生する確率 有意性 キャンペーン・トレーディングに対する影響 相関のある資産曲線 賭け戦略に対する影響 まとめ
第7章 マルティンゲール単純なマルティンゲール複雑なマルティンゲール 原油のマルティンゲール
第8章 トレーディングの管理ポートフォリオの影響日々のトレーディング 詳細 通常の経路 勝ちトレードと負けトレードを定義し直す 関連するインディケーター 終値の使用 まとめ
付録A――MAEの計算 |
トレード戦略を考える場合、アルゴリズムそのものをあれこれといじろうとする人は多いが、ポジションを取ったあとの損益の行方を管理しようとする人は少ない。なぜならそれはリスク管理の範疇に属する話であり、研究してもつまらないと一般的には思われているからだ。だが、専門家とそうでない人を分けるもののひとつはこのリスク管理にある。トレードに限らず、リスクもリワードも、本来はあるインシデントが発生する確率(頻度)と、それが起こったときのインパクト(影響)との積(以下単に、「積」)で表されるものである。そして、それを正しく認識するためには統計的な解析が欠かせない。
だが、リスクについては、専門家は発生の頻度と影響の両方に注目する傾向があるのに対し、多くの人は損害の頻度か影響のどちらかのみを重視する傾向がある。一方で、リワードについては、専門家はその頻度と影響の両方に注目するのに対し、ほとんどの人はその積のみを重視する。私たちの脳が現実世界を必ずしも正しく認知するとは限らないゆえに、こういったことはいたしかたがないことではあるが、結果として、いびつなトレード戦略をそれと知らずして使用していることになりかねないのである。
本書で紹介されたような分析をトレード戦略の実行フローの各段階で行うことによって、こうした意図せざるバイアスを避けることができるだろう。リスクに関して言えば、私たちはペリル(インシデントの発生)をコントロールすることはできないが、ハザード(リスクの潜在的背景)に対するイクスポージャー(露出)をコントロールすることは可能である。資産運用において起こる悲劇のほとんどはこれを適切に管理すれば避けることができる。逆に言えば、その概念をリワードに応用すれば、効率的な利益の上げ方も同様に見いだすことが可能なはずである。本書が、自分のトレード戦略の改善を試みる読者のための一助となることを願うものである。
翻訳にあたっては以下の方々に心から感謝の意を表したい。翻訳者の山下恵美子氏は丁寧な翻訳を実現してくださった。そして阿部達郎氏にはいつもながら丁寧な編集・校正を行っていただいた。また本書が発行される機会を得たのはパンローリング社社長の後藤康徳氏のおかげである。
2012 年9月
長尾慎太郎
先物・オプション業界はすでに揺籃期を脱し、成熟期に入ろうとしている。つまり、開拓マシンとしての役割りを終え、最もアクティブな世界市場の中心的存在へと変貌しつつあるということである。通貨市場におけるEFP(現物と先物のポジションを交換する)取引の導入によって、現物市場も先物市場も当事者にとって利便性の高いものになると同時に、先物市場は世界の穀物の正式な値決めの基準に使われるようになった。株式ポートフォリオのヘッジ、クロスレートの設定、スワップ取引、インフレ指数連動債の購入も、今やトレーダーや投資マネジャーは電話1本で実行可能だ。古くから存在した制度間の違いもほとんど消えつつある。
しかも、これはほんのプロローグにすぎない。伝統的なオープンアウトクライ市場にも電子の波は確実に押し寄せ、今では、ピットでの取引から事後処理に至るまでのすべてがコンピューターで処理されている。「プログラムトレーディング」は、コンピューター化されたティッカーテープを分析し、自動的に売買を執行する手法であるが、これもまた避けることのできない変革プロセスの氷山の一角にすぎない。注文執行がすべてコンピューター化され、執行に関してだれにも苦情を言えなくなる日は、もう目前まで来ている。やがては、オーダーさえ出さなくても済む日がやって来るだろう。
市場の変革に伴って、市場関連の書籍もまた進歩した。しかし、トレーディングについて書かれた書籍の多くは入門書の域を出ない。高度な読者向けに書かれたものさえ、取引についての細々とした記述や市場のメカニズムについての説明を含むものが多い。経験豊富なプロのトレーダーやアナリスト向けの内容に焦点を絞り込んだ書籍が少ないのが現状だ。こういった状況のなか、The Trader's Advantageシリーズはまさに彼らの待ち望んだ書籍を提供するものである。 本シリーズの書籍はすべて、その道のプロと優れたリサーチアナリストの手によって書かれたものだ。内容は主として先物、現物、株式の各市場を対象とするものだが、価格予測にも応用可能である。本シリーズで扱う題材にはトレーディングシステムと各種テクニックも含まれるが、これらはすべて、価格予測とトレーディング技術を磨くうえで不可欠なものばかりであるため、本シリーズに含めた。
クリエイティブで最先端の内容を扱う本シリーズは、新しいテクニック、既存のトレーディング手法の徹底分析、未解決問題への新たな取り組み方を提示するものである。本シリーズでは、概念は明確で分かりやすく説明し、例題と図表をふんだんに取り入れるという一貫した姿勢が貫かれている。また、不必要な基礎的資料を含んでいないため、ボリュームは抑え気味で、要点を明確に述べているのがシリーズ全体の共通点である。読者には注意深い読みと考察が求められるが、本シリーズを読破することで、市場分析と市場予測のあらゆる分野に対する理解は、類書とは比較にならないくらい高まるだろう。
物事を深く洞察する天賦の才がないかぎり、トレーディングで成功するには相当の努力が必要だ。誇れる実績を持つ人々は、政府が発表する指標・統計・報告書に対する市場の反応、市場ボラティリティの変化、市場の動く速さ、市場間の関係、1日を通して流動性の低下する時間帯などについて長い時間をかけて研究・学習したからこそ、そういった実績を上げることができたのである。成功するトレーダーはこうした絶え間ない努力の結果として、無数のパターンのなかから利益の出るパターンを見つけだし、利益を上げることができるのである。
こうした努力のなかから彼らが得た最も重要な「洞察」は、おそらくはリスクを理解することの重要さではないだろうか。市場で取るどういったポジションにもリスクは付き物だ。リスクを表すのによく使われる尺度は価格変動(ボラティリティ)だが、各トレーディングスタイルやシステマティックなアプローチはそれぞれにリスクに対する独特のエクスポージャーパターンを持つ。例えば、ロングポジションを何カ月にもわたって保有することが多い長期トレンドフォローシステムは、数時間で仕掛けと手仕舞いを繰り返すデイトレーディングよりも1トレードにおける潜在的利益も損失も大きい。しかし、勝ちトレードと負けトレードの現れる順序によって資産曲線は大きく違ってくる。買いや売りのルールを設けるとき、そのトレーディング手法特有の価格の逆行パターンというものを理解しなければならない。こうしたリスクを調べ、管理することが重要なのである。リスク管理なくして生き延びることは不可能だ。
ジョン・スウィーニーは、過去に現れ、将来的にも再び現れることが予想される、われわれを悩ますこうした大きな価格変動を「最大逆行幅」と名づけた。実際のパフォーマンスが予測されたものと異なるのは、こうした資産のドローダウンによるところが大きい。実際のドローダウンが予想されたものよりも大きければ、理論的にいかに優れたプランでも見直しが必要になる。資産変動を現実的かつ実用的に評価するうえで役立つのが価格の逆行であるとジョン・スウィーニーは言う。価格の逆行を評価することは簡単にできるうえ、徹底した評価を行うことでリスク管理のためのルールを作成することができる。したがって、パフォーマンスの大幅な改善が期待できるというわけだ。
どのトレーディング手法にもそれぞれに独特の価格の逆行パターンというものがある。こうしたパターンを体系的に調査することで、それぞれのトレードに投下すべき資金額が分かり、さらには損切り水準、つまりそれぞれのトレードで取るべき最大リスクも分かる。一連のトレードに対する逆行パターンを見つけることができれば、パフォーマンスの大幅な改善につながる。さらにジョン・スウィーニーはこの概念を一歩進め、利益や損失が出たあとで投資額の大きさを変えることでトレーディングプログラムのリターンやリスクを改善するための方法についても論じている。
本書ですべてのトレーディング手法を取り上げることは不可能だが、読者は本書で学んだツールと理解したことをもとに自らの手法を検証することができる。また、巻末には付録としてエクセルコードや実例も豊富に提供されている。ワークブックとして本書と並行して使ってもらいたい。
本書の素晴らしさは、資産の逆行や順行という概念を秩序立ててまとめ、その評価方法を分かりやすく示している点にある。簡単で理解しやすい方法で示すことほど読者にとってありがたいことはない。ステップバイステップで分かりやすく書かれた本書を読み終えるころには、自分のトレーディング手法の資産の逆行スイングを注意深く評価することがどれほど重要で利益に結びつくものであるかが理解できているはずだ。
ペリー・J・コーフマン(バーモント州ウエルズリバーにて)
こうした人々にとって、本書はリスクを評価し損失を最小化するための斬新な方法を手に入れるためのうってつけの書となるはずである。先物の世界はゼロサムゲームである。勝者がいれば、それに対する敗者が必ずいる。これに対して市場が拡大しつつある株式トレーダーは楽かもしれない。だれもが勝者になれるからだ(全員が敗者になることもあるが)。しかし、先物ゲームは株式ゲームとは違って厳しい(「ゲーム」という言葉が重要)。私が勝てば、あなたは負ける。しかし手数料や「スリッページ」を計算に入れれば、わたしたちはどちらも敗者である。
こうしたトレーディング環境や数学理論から言えば、勝つための鍵は最大損失を最小化することであることは容易に察しがつく。どういったトレーディングの格言についても言えることだが、問題はどれくらいの大きさであればよいのか、である。最大損失を数値化するにはどうすればよいのだろうか。本書ではこれを解説していく。本書が斬新というのはこういう意味である。
まずは物事を定量化するために、いつも使っている自分のトレーディング手法の結果を見てもらいたい。樹皮や枝ばかり見る人は、森の動きを見逃している可能性がある。少なくともビジネスサイクルの小さな風に振り回されている可能性が高い。詳細な日記を付け、それを読み返す習慣のない人は、仕掛けたあとの市場の動きに規則性があったとしても、おそらくは気づかないだろう。仕掛けたあとの状況はそれぞれに異なる。状況をきちんと把握し賢くトレードする人が大金を儲けられるのはそのためだ。
行動を起こそうとするときにいつも規則的なパターンが発生するはずがないではないか、とあなたは思うかもしれない。しかし、損切りすべきときを第六感ではなく客観的に知ることができるとしたらどうだろう。プロテクティブストップを置くべき時期を客観的に知ることができるとしたらどうだろう。利食いすべき時期を客観的に知ることができるとしたらどうだろう。もしこれらがすべて可能だとしたら、あなたがやるべきことは自分のプランを正しく実行するだけである。
マネジメントの面から言えば、あなたの行ったトレードが賢明なトレードだったのか単なる幸運にすぎなかったのかを評価する方法があったとしたら? 最良で最も賢明なトレーダーをぐうの音も出ないほど非難し続けるよりも、一貫して勝ち続ける方法があったとしたら? 客観的なパフォーマンス基準を設定し、トレーディングスタイルや手法に基づき必要な資金額を算出し、避けることのできない損失が標準的なものなのか異常なほど大きなものなのかを評価することができたとしたら?
本書で紹介するのはこうしたことを可能にする方法である。しかし、こういった方法はタダでは手に入らない。市場の振る舞いを綿密に調べ、操られにくいツールを使わなければならない。本書では意思決定をするときに起こること、つまり市場の振る舞いの結果としてわれわれのポジションがどうなるのか、に注目する。つまり、「われわれが常に意思決定を行っていれば、市場は何をするのだろうか」ということである(これは、「われわれが常に意思決定を行っていれば、利益を出すことができるのだろうか」とは異なることに注意)。今日こう聞かれれば、「分からない」「市場はランダムだから成り行きに任せるしかない」、あるいはもっと悪いことに、「きっと勝ちトレードになるはず」(負けると分かっているトレードをわざわざ行う人はいないから)と答えるしかない。
正解に最も近いのは、「分からない」という答えになるだろうか。考えてもみてほしい。もし市場が本当にランダムなら、だれもトレーディングなんてしないはずだ。というよりも、トレーディングは不可能、と言ったほうがよいかもしれない。市場が本当にランダムなら、次の価格が前の価格に近いことはほとんどなく、まったく違ったものになるからだ。
投機的なトレードは勝つこともあれば、負けることもあり、イーブンのときもある。われわれが興味があるのは勝ちトレードであり、負けトレードはできるだけ早く見つけて損切りすることで損失を最小限に抑えたい。自分のやっていることが分かっていれば、勝ちトレードになるものと負けトレードになるものは違うように見えるということが分かるはずだ。「どう見えるか」を知ることが成功につながる鍵なのである。
「どう見えるか? それはどういう意味なのか」とあなたは思うだろう。本書では市場の振る舞いをデータの集合体であるグラフで示すため、この場合の「見える」は「予想される」を意味する。本書では市場の振る舞いを価格チャートではなく統計学的図表で示す。
これらの図表から得られるものこそが、あなたとほかのトレーダーとを分ける線、つまりすべてのトレーダーたちが探し求めるエッジ(優位性)であり、このエッジさえ手に入れれば定量化できる最小限のリスクで利益がよどみない流れとなってあなたのもとに押し寄せるのである。
市場は規則正しい振る舞いを見せるのだろうか。市場の振る舞いのなかに規則性があることを証明できるのだろうか。もしそうなら、どうやって? 心をオープンにして本書を読み進めてもらいたい。回答はやがて明らかになるはずだ。
本書がトレーダーにとって統計学の入門書になると感じたのは、私が本書の原稿を書いているときだった。トレーディングの本と言えば、チャートやライン、インディケーターというのが相場だ。本書ではそれらをすべて、トレーダーたちがあまり使うことのないグラフと表で置き換えた。本書は、実践に役立つ逆行・順行分析の基本を教示することを目的としたものであるため、理論についてはそれほど深く掘り下げて議論することはしない。
また、一般論ではなく実例を使って分かりやすく説明しているのも本書の大きな特徴だ。いまやコンピューターを使わないトレーダーはほとんどいない。したがって、だれもが入手可能なスプレッドシートを使った。データ分析にはもっと高度なソフトウエアを使うこともできるが、そういったソフトウエアを使いこなすには統計学の知識とプログラミング能力が不可欠だ(試しに高度な科学技術計算ソフトであるマスワークス社のMatlabを見てもらいたい。その難しさがよく分かるはずだ)。
幸い、私たちが使うデータは単純なものなので、簡単な統計学で事足りる。さらに、逆行幅の測定テクニックを学ぶのにもそれをグラフ化するのにも、難しい数学は使わないので、数学があまり得意でない人も心配はいらない。このように本書で提示する内容には限界はあるものの、あなたのトレーディングに応用できるものは多いはずである。
1996年10月 ワシントン州シアトルにて
ジョン・スウィーニー
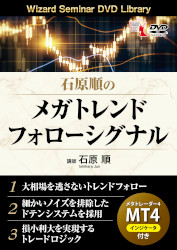 DVD 石原順のメガトレンドフォローシグナル |
 利食いと損切りのテクニック |
 ラルフ・ビンスの資金管理大全 |
 投資家のためのマネーマネジメント |
 トレーディングシステム入門 |